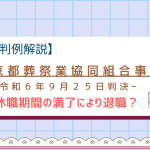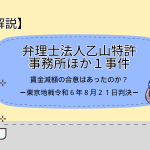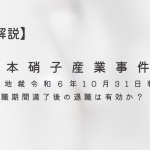休職期間満了による自然退職は有効か?【職場のパワハラ】【TCL JAPAN ELECTRONICS 事件】
- 当社は、川崎市内でコンサルティング業を営んでいます。当社の従業員がメンタルの不調で業務に就くことができなくなったことから、就業規則に基づいて休職を命じました。その後、従業員から復職願が出ましたが、当社の顧問医に診てもらったところ、まだ復職できる状態ではないとのことでしのたで、復職を命じることができず、その結果、休職期間満了で自然退職となってしまいました。その後、当該従業員から、「復職は可能だった」「メンタルの不調は業務に起因するもので自然退職とすることはできない」との主張が出されました。当社の対応に問題はありますでしょうか。
- 休職命令は、休職期間満了までの間、解雇を猶予するものです。そのため、「休職事由が消滅したとき」とは、職員が雇用契約で定められた債務の本旨に従った履行の提供ができる状態に復することであって、原則として、従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合、又は、当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうと考えられています。そして、休職事由の消滅については、解雇を猶予されていた職員において主張立証しなければならないとされています。
ご質問のケースの場合、従業員の側から復職可能性(従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった)を証明しないといけません。
ただし、メンタルの不調が業務に起因するものである場合は、労働基準法19条1項の類推適用によって、休業期間中及びその後30日間は退職の効果は生じないとされる可能性があります。
詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)については、事業主の措置義務などが法律で定められています。
特に、令和4年(2022年)4月からは、中小事業主も含めて、このようなパワハラ防止措置義務を負うことになり、会社の規模や業種などに問わず、すべての会社がハラスメント防止に向けた対策に真剣に取り組むことが求められています。
しかし、残念ながら、いまだに多くの会社では、パワハラ、マタハラ、セクハラをはじめとするハラスメント行為があとをたちません。
近年では、これらのハラスメントに加えて、カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)や就活等ハラスメントも大きな問題となってきています。
改めて、職場におけるハラスメントについて防止対策がきちんとできているのか?従業員のハラスメントに対する意識に問題点はないか?会社のハラスメント対策が周知・徹底されているか?などを確認し、見直しを図ることが大切です。
職場におけるハラスメントについてお悩みがある場合には、弁護士に相談してみることもおすすめです。
裁判例のご紹介(TCL JAPAN ELECTRONICS 事件・東京地裁令和5年12月7日判決)
さて、今回は、職場においてパワハラを受けた被害者が、休職期間満了に伴って自然退職とされたことについて、退職の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

*労働判例2025.10.15(No.1336号)62ページ以下参照*
どんな事案?
この事案は、Y社と雇用契約を締結して就労していたXさんが、Y社の代表取締役や副社長、直属の上司からパワハラを受けるなどした後に適応障害を発症して、休職したところ、Y社が休職期間満了前に休職事由が消滅したと認められないとして自然退職扱いとしたことは無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の地位の確認や未払い賃金の支払いなどを求めた事案です。
何が起きた?
Xさんについて
Xさん、B大学教育学部を卒業後、平成26年4月から平成27年3月までは公立中学校において教員として勤務し、また同年9月から平成29年7月まではラグジュアリーブランドの店舗、百貨店及びホテルで勤務していました。
そして、平成30年6月1日にY社に入社しました。
Y社について
Y社は、平成27年9月3日に設立された中国C省D市に本社を置くTCLグループの日本法人であり、アマゾンのECサイトやディストリビュータ2社を通じて日本国内でTCLグループの電機製品を販売していました。
平成31年3月時点のY社の従業員数は11名であり、従業員はフルタイムで勤務し、複数のポジションを兼任する者も多く存在しました。
XさんとY社との間の雇用契約
Xさんは、Y社との間で、平成30年6月1日、本件雇用契約を締結しました。
Xさんは、入社当初、営業本部計画物流部物流担当に配属され、同年8月から総務部総務担当と兼務となっていました。
しかし、Y社の組織変更後、Xさんは人事総務部庶務担当に配属され、物流担当ではなくなりました(本件配置転換)。
Xさんに対する退職勧奨①
Y社は、平成31年3月8日、Xさんに対し、XさんがGの業務上の指示に反抗してトラブルを発生させ、Y社の業務に重大な影響を及ぼしたなどと告げたうえ、退職勧奨を行いました(本件退職勧奨〈1〉)。
本件退職勧奨〈1〉の条件は、Xさんが本日付けで退職勧奨に応じ、翌週に業務引継ぎを終えれば、その後は出勤しなくても同年3月分の給与及び60日分の平均賃金を支払うというものでした。
また、Xさんが退職勧奨に応じない場合、就業規則24条1号、2号及び6号違反を理由に訓戒処分と反省文の提出を求めることが予告されました。
Xさんに対する訓戒処分
Y社は、同月22日、Xさんに対し、上長の指揮命令に従わず、上長に反抗的な態度を示し、反省を拒むこと及び会社の管理体制系統を無視し、飛越行為を繰り返したことが就業規則24条1号、2号及び6号の1に該当することを理由に訓戒処分とすること及び同日から1か月を限度として、Xさんの職務遂行を審査すること等が記載された訓戒処分通知書を交付しました(本件訓戒処分)。
そして、Y社は、Xさんに対して、同月25日までに、本件訓戒処分を厳粛に受け止め、上長の指揮命令に従うこと等本件訓戒処分通知書に記載された指示事項に従い、誠実に勤務し、これが履行できない場合には、いかなる処分を受けても異存ない旨記載された誓約書に署名押印して提出することを求めました。
Xさんに対する退職勧奨②
さらに、Y社は、Xさんに対し、一身上の都合ではなく合意退職とすることも可能であるなどして、再度の退職勧奨を行いました(本件退職勧奨〈2〉)。
適応障害の診断
Xさんは、同月25日、かねてより通院していたH(心療内科)を受診し、適応障害の診断を受け、少なくとも4月末までの自宅療養を要するとのI医師の指示を受けました。
そして、Xさんは、その旨記載された診断書(3/25付け診断書)をY社に提出し、同日以降欠勤しました。
休職命令
同月29日、Y社は、Xさんに対し、同月25日から同年6月24日までの3か月間の休職を命じる旨通知しました(本件休職命令)。
復職願の提出と休職期間の延長
Xさんは、令和元年6月17日、Y社に対し、J医師作成の同月14日付け診断書(6/14付け診断書)を添付し、同月24日に復職したい旨記載した同月17日付け復職願を提出しました。
6/14付け診断書には、「症状寛解し、現在通勤訓練を行い順調な回復を認めるので、6月15日以降就労可能である。但し、当初は4時間程度より開始しその後2ケ月間程度の期間を経て定時勤務とすることが望ましい。」と記載されていました。
しかし、Y社は、同月24日の復職を認めず、Xさんの休職期間を同年10月24日まで延長しました。
休職期間満了による退職扱い
Xさんは、同年8月29日頃、Y社に対して、J医師作成の同日付け診断書(8/29付け診断書)を提出しました。
8/29付け診断書には、適応障害は寛解したこと、前回診断に引き続き就労可能であるが、当初は4時間程度より開始し、その後2か月程度の期間を経て定時勤務とすることが望ましいことが記載されていました。
ところが、Y社は、同年11月15日、Xさんに対し、延長後休職期間満了日である同年10月24日時点でも休職事由が消滅したとは認められなかったため、就業規則39条4項に基づき、同日をもって自然退職となった旨を通知しました。
訴えの提起
そこで、Xさんは、Y社が休職期間満了前に休職事由が消滅したと認められないとして自然退職扱いとしたことは無効であると主張して、Y社に対し、雇用契約上の地位の確認や未払い賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)
Xさんが主張していたこと
この裁判において、Xさんは、令和元年6月17日時点で休職事由は消滅しており、就業規則に定める退職事由には当たらないことから、Y社による退職取扱いは無効であって、本件雇用契約は継続している、と主張していました。
Y社が反論していたこと
これに対して、Y社側は、Xさんは、令和元年6月17日時点において(及び同年10月24日時点においても)、時短勤務であれ就労不能な状態が継続しており、相当期間内に治癒が見込まれる状態であったとは認められないなどとして、休職事由が消滅したとは認められない、と反論していました。
裁判で問題になったこと(争点)
そこで、この裁判では、令和元年6月17日時点で休職事由は消滅していたといえるかどうか?が問題(争点)になりました。
なお、この裁判では、この他にもパワハラ行為の有無などが争われている点がありますが、本解説記事では省略しています。
裁判所の判断
この点について、裁判所は、令和元年6月17日時点で休職事由は消滅していたとはいえず、休職期間満了までに休職事由が消滅したとも認められない、としてXさんの主張を退けました。
※ただし、原告の適応障害は被告の業務に起因して発症したものと認められることから、労働基準法19条1項類推適用によって自然退職は認められず、結論としては、原告の雇用契約上の地位の確認の請求は認められました。(控訴後和解)
本判決の要旨(ポイント)
なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?
以下では、本判決の要旨(ポイント)をご紹介します。
Y社就業規則39条4項の「休職事由が消滅」の意味とは?
まず、裁判所は、Y社の就業規則に定める「休職事由が消滅したとき」の意味合いについて、「職員が雇用契約で定められた債務の本旨に従った履行の提供ができる状態に復すること」であると示しました。
「Y社の就業規則は、社員が同38条各号に定める休職事由に該当するときは休職を命ずることがあり、休職期間満了後においても休職事由が消滅しないときは休職期間満了の日をもって自然退職とする(同39条4項)と定めている。このような就業規則の定めによれば、Y社において、休職命令は、休職期間満了までの間、解雇を猶予するものであるということができる。そうすると、「休職事由が消滅したとき」とは、職員が雇用契約で定められた債務の本旨に従った履行の提供ができる状態に復することであり、原則として、従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合、又は、当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった場合をいうと解するのが相当である。そして、休職事由の消滅については、解雇を猶予されていた職員において主張立証しなければならないと解するのが相当である。」
Xさんの状況について
そして、裁判所は、Xさんの休職事由が消滅していたかどうかを検討し、医師の意見書の内容や診断書などからすれば、令和元年6月17日時点において、Xさんが「当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」とは認められない、と判断しました。
▶︎本件休職命令の満了時点において「従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」とはいえない
「認定事実(…)によれば、本件休職命令の満了時であった令和元年6月24日時点において、Xさんは就労可能とされていたものの、最初の2か月間程度は4時間程度の勤務とすることが望ましいとの留保が付されていたことからすれば、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」とは認められない。
▶︎令和元年6月17日時点において、「当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」とはいえない
「(…)6/14付け診断書には「症状寛解し、現在通勤訓練を行い順調な回復を認めるので、6月15日以降就労可能である。」との記載があることが認められる一方、診療録(…)を見ると、令和元年6月6日時点で身体化の出現が見られなかったことから復職へトライするとの方針が示されるも、同月14日時点では午前8時半に会社に行くことはできたが一瞬で帰ったことを話しながら涙ぐむ場面があり、なお不安動揺が残存しているとの所見が示されていること、同年7月12日時点でも3回悪夢を見たとの訴えがあり、流涙絶えず、翌週の第1回団体交渉で会社と話をするのが怖いとの訴えがあり、刺激により別人のように表情が変わると指摘されていること、同月16日には持病の心臓発作があり、その原因として会社絡みと怒りがのってきたことと説明していること、同月26日時点では、元気であるが、会社には行けない状態との訴えがあったこと等が認められる。また、J医師の意見書(…)においては、同年6月16日時点では出勤したものの負荷状況による流涙などの臨床症状が再出していたとの意見が述べられ、6/14付け診断書において寛解と判断した具体的な説明はなされていないことが認められる。これらの診療経過及びJ医師の意見書の内容を考慮すれば、同月17日時点において、Xさんには会社で就業することへの精神的負荷による流涙等の臨床症状が発現する状況がなお残存していたものであり、このような状況において、「当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」と認めることはできない。そして、8/29付け診断書の内容は6/14付け診断書の内容と大差なく、その他に同年10月24日の休職期間満了時点までに「当初軽易作業に就かせればほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態になった」と認めるに足りる証拠はない。
結論
このような検討を踏まえ、裁判所は、令和元年6月17日時点で休職事由は消滅していたとはいえず、休職期間満了までに休職事由が消滅したとも認められないとの結論を導きました。
「以上によれば、同年6月17日に休職事由が消滅したとのXさんの主張は採用できず、休職期間満了までに休職事由が消滅したとも認められない。」
弁護士法人ASKにご相談ください
さて、今回は、職場においてパワハラを受けた被害者が、休職期間満了に伴って自然退職とされたことについて、退職の有効性が争われた事案をご紹介しました。
本判決では、「休職事由が消滅したとき」には当たらないとして、休職事由が消滅していたとの従業員側の主張を退けています。
休職事由が消滅していたといえるかどうかについては、会社と従業員との間で意見が食い違うことが多く、主治医と産業医との間でも見解が異なるといったケースも見られます。
したがって、休職をした従業員について、会社として復職を認めるかどうかの判断をする場合には、個々の事案に沿って、慎重に検討することが大切です。
従業員の休職や復職などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)