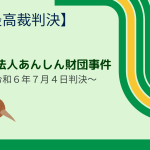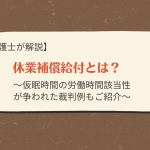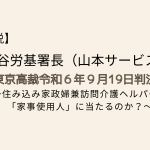業務中の事故による負傷について業務起因性が認められるか?【東京地裁令和5年3月17日判決】
Recently updated on 2025-06-02
- 川崎市内で建設業を営んでいます。当社の従業員が現場に向かう最中、追突事故で頸椎捻挫や腰椎捻挫の怪我を負いました。通院をしていたのですが、他の部位も痛くなったようで、その部分の治療も障害補償給付の申請したところ、認められませんでした。業務中の事故なのに労災補償が認められないことがあるのでしょうか。
- 労災補償が認められるには、業務と傷害との間に一定の因果関係(業務起因性)があることが必要になります。事故と無関係な傷害(障害)については業務起因性が認められず、給付申請が認められないことがあります。今回のご相談の場合、他の部位の痛みの発生が一般的に追突事故により生じうるものか、他の要因はないか、事実経過が整合的かなどを判断し、業務起因性が認められれば、労災補償が認められる可能性があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、併せて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
被災労働者やその遺族が受けられる保険給付は、それぞれの労働災害の内容や種類などによって異なります(厚労省HP:「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」参照)。
今回は、その中でも、休業補償給付と障害補償給付の支給をめぐって、業務起因性の有無が争われた裁判例についてご紹介します。
| 休業補償給付 | 労働者が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり療養のため働くことができず、そのために賃金を受けない場合、その4日目から支給される |
| 障害補償給付 | 業務上又は通勤による傷病の治ゆの後、身体に一定の障害が残った場合に支給される |

裁判例のご紹介・東京地裁令和5年3月17日判決
どんな事案?
本件は、業務中に追突事故に遭い傷害を負った労働者が、休業補償給付と障害補償給付の請求を行ったところ、不支給決定等を受けたことから、同決定の取消しを求めた事案です。
何が起きた?
業務中の事故の発生
Xさんは、建築作業などに従事する労働者でした。
業務中、Xさんが中型貨物自動車を運転していたところ、渋滞で停車中に追突事故に遭いました(本件事故)。
Xさんの通院①
Xさんは、緊急搬送先のH1病院で、頭部打撲(全治約7日間)腰椎捻挫及び右下腿部打撲血腫(全治14日間)の診断を受けました。
そして、Xさんは、紹介されたH2病院で治療を受けました。
本件事故の3か月後、Xさんは、H2病院において、「首、腰の痛みは続いている」としつつも、症状固定(治ゆ)の判断を受けました(初回症状固定判断)。
Xさんの通院②
もっとも、Xさんは、初回症状固定判断に不満を持ち、転医を希望しました。そして、再びH1病院を受診し、腰痛・右肩痛などを訴えました。
これに対して、医師は、Xさんの右肩に腱板断裂及びインピンジメント症候群を認めました。
そして、Xさんは、腰痛についてH1病院を治療を受け、右肩については紹介を受けたH3病院で治療を受けました。
本件事故の7か月後、Xさんは、「頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肩腱板不全断裂」について症状固定の判断を受けました。
休業補償給付の請求
Xさんは、本件事故に付随する通院期間①、通院期間②について、それぞれ休業補償給付の請求を行いました。
| 通院期間① | 本件事故から初回症状固定判断までの約3か月間 |
| 通院期間② | 通院期間①に続く約4か月間 |
これに対して、処分行政庁は、初回症状固定判断を前提として、通院期間①については支給決定を行い、通院期間②については不支給決定をしました。
障害補償給付の請求
また、Xさんは、障害補償給付の請求を行いました。
処分行政庁は、一旦は、右肩腱板不全断裂に業務起因性があることを前提として併合10級とする障害一時金の支給を決定しました。
ところが、処分行政庁は、業務起因性を否定し、同等級を14級とする変更決定をしました。
訴えの提起
そこで、Xさんは、Y(国)に対し、通院期間②についての休業補償給付不支給決定の取消しと、障害補償給付にかかる等級の変更決定の取消しを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?
本件では、Xさんの右肩腱板不全断裂が本件事故によるものであったかどうか(=業務起因性が認められるかどうか)が問題になりました。
裁判所の判断
裁判所は、Xさんの右肩腱板不全断裂が本件事故によるものであったとして、業務起因性を認めました。
※なお、結論としては、障害補償給付にかかる等級の変更決定の取消しに関する請求を認めた一方、本件事故による傷害は初回症状固定判断の時点で症状固定していたとして、通院期間②についての休業補償給付不支給決定の取消しに関する請求は棄却しています。
判決のポイント
本判決は、腱板断裂が外傷性か非外傷性かを判断することは容易ではない、との医学的な知見の存在を認定した上で、
- ①本件事故によって右肩腱板不全断裂が生じた可能性があること
- ②右肩腱板不全断裂を生じさせる他の原因がないこと
- ③本件事故によって右肩腱板不全断裂が生じたという事実が具体的な事実経過と整合的であること
からすれば、Xさんの右肩腱板不全断裂が本件事故によるものであると認めています。
判決の要旨
①本件事故によって右肩腱板不全断裂が生じた可能性があること
「(…)肩腱板不全断裂は、一般的に、単一の外傷が主要な誘因となって生ずることは少ないが、そのような事例も存在し、交通事故は単一の外傷により損傷が生ずる場合の主要な要因の一つであることが認められる。したがって、本件事故において、肩関節付近への直達外力(損傷部位に直接作用する外力)があったとすれば、それが原因となって原告の右肩腱板不全断裂が生じた可能性を肯定することができる(…)。
したがって、本件事故は、Xさんの右肩腱板不全断裂を生じさせ得るものであったというべきである。」
②右肩腱板不全断裂を生じさせる他の原因がないこと
「Xさんの右肩腱板不全断裂については肩関節の可動域制限を生じさせるものであるところ、(…)Xさんが本件事故の前には肩に不調を感じておらず、(‥)業務も支障なく行えていたことに照らせば、Xさんの右肩腱板不全断裂は、本件事故以後に生じたものとみるのが相当である(…)。
以上のことを考えあわせれば、Xさんの右肩腱板不全断裂が、本件事故の後に、他の原因により生じたとみることもできない。」
③本件事故によって右肩腱板不全断裂が生じたという事実が具体的な事実経過と整合的であること
「(…)Xさんは、本件事故後およそ2週間以内に右肩の痛みにつきG病院の医師に申告した旨を供述しているところ(…)Xさんが、平成31年4月15日(本件事故の6日後)に肩の痛みを申告している事実と整合し、信用することができる(…)。
したがって、本件事故によってXさんの右肩腱板不全断裂が生じたとすることに、客観的な事実との間に不整合もない。」
結論(右肩腱板不全断裂は本件事故によって生じたものと認められる)
「以上の(…)検討の結果によれば、本件事故はXさんの右肩に腱板損傷を生じさせるようなものだったということができる一方で、本件事故の他に右肩腱板損傷の原因となるものが見出だせず、また、本件事故によって右肩不全断裂が生じたとみることを妨げる事情もない。そうすると、Xさんの右肩腱板不全断裂は、本件事故によって生じたものと認めるのが相当である。
したがって、第2事件に係るXさんの請求には理由がある。」
弁護士にもご相談ください
今回ご紹介した裁判例では、業務中に発生した事故について、労災における業務起因性の有無が問題になっていました。
業種によっては使用者がいくら注意をしていても、労働者が事故に遭ったり、怪我をしてしまったりすることがあります。
しかし、使用者(会社)には労働者に対する安全配慮義務があることから、常にリスクチェックを怠らないように注意が必要です。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
業務中の事故や従業員の負傷などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)