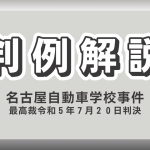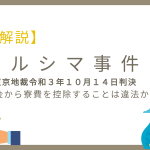時給制契約社員に寒冷地手当を支給しないことは許されるのか?【日本郵便(寒冷地手当・札幌)事件】
- 労働問題
- tags: パートタイム・有期雇用労働法 労働判例解説 同一労働同一賃金
- 当社は、全国に支店を持っております。当社には、全国転勤のある正社員と現地採用で有期雇用の契約社員の2種類の社員がいます。全国転勤のある正社員を寒冷地に赴任させる際には「寒冷地手当」として冬期のみ月1万円を支給していますが、有期雇用の契約社員にはこれを支給していません。ある契約社員から、これは不公平ではないかという指摘を受けました。当社の制度は違法でしょうか。
- パートタイム・有期雇用労働法8条においては、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。」と定められています。「寒冷地手当」が「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違」と判断された場合、契約社員に対して寒冷地手当を支給しない規定が無効と判断されるおそれが否定できません。
詳しくは、企業側の労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
手当とは
賃金にはさまざまなものがあります
賃金の支払いは、会社が労働者に対して負う最も重要な義務の一つです。
「賃金」と言っても、単に給料だけではありません。
賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として労働者に対して支払われるすべてのものが「賃金」に当たります。
諸手当は各事業場によって異なります
諸手当は、基本給を補充するものとして支給されるもので、支給条件に該当している場合にのみ支給されるものです。賞与等の算定基礎とならない等の性格を持っています。
例えば、通勤手当や住宅手当、家族手当などの名称で支払われることが多いですが、どのような手当を設けるか、また、設けた諸手当の金額をいくらにするかについては、それぞれの会社で決めることになります。
寒冷地手当が支給されていることもあります
ところで、「寒冷地手当」という手当を聞いたことはあるでしょうか。
多くの寒冷地域では、冬季における暖房用燃料費等が、その他の地域に比べて非常に高額なものとなります。そこで、会社によっては、勤務地域が異なることによって増加してしまう生計費の負担を緩和し、社員相互間の公平を図る観点から、寒冷地域に勤務する社員に対しては、暖房用燃料費等にかかる生計費の増加の程度に応じて手当を支給しています。
このような手当が寒冷地手当です(暖房手当と呼ばれることもあります)。
どうやら最近では、民間企業において、この寒冷地手当を廃止するケースが増えているようです。これから先どうなるのか不安が残ります。
裁判例のご紹介(日本郵便(寒冷地手当・札幌)事件・札幌地裁令和5年11月22日判決)
さて、ここからは、寒冷地手当を正社員に対しては支給する一方、時給制契約社員に対しては支給しないとする労働条件の相違が、旧契約法20条に違反するか否かが争われた裁判例をご紹介します。
事件アイキャッチ.png)
どんな事案?
本件は、Y社と有期労働契約を締結している時給制契約社員のXさんらが、Y社が無期労働契約を締結している労働者には寒冷地手当を支給する一方で、Xさんらには寒冷地手当を支給しないことが、旧労働契約法20条に違反すると主張し、Y社に対して損害賠償を求めた事案です。
何が起きた?
XさんらとY社の関係
Y社は郵便業務等を営む会社でした。
Xさんらは、Y社との間で有期労働契約を締結して、以後、Y社との間で更新を繰り返している時給制契約社員でした。
時給制契約社員と正社員との労働条件の相違
就業規則と給与規程のちがい
Y社に雇用される従業員には、無期労働契約を締結する労働者(正社員)と有期労働契約を締結する期間雇用社員が存在し、それぞれに適用される就業規則及び給与規程が異なっていました。
給与のちがい
《正社員の場合》
正社員の給与は、社員給与規程に基づき、基本給と諸手当で構成されていました。
基本給は全国一律となっていました。
また、諸手当の一つである寒冷地手当は、勤務する地域の区分、世帯主か否か、扶養親族の有無によって金額が定められていました。
《時給制契約社員の場合》
他方、時給制契約社員の基本給は、期間雇用社員給与規程に基づき、基本賃金と諸手当で構成されていました。
基本賃金は、地域別最低賃金の相当額に20円を加算した額を下限として、募集環境も考慮しつつ予算の範囲内で所属長が決定していました。
そして、時給制契約社員については、寒冷地手当は支給されないことになっていました。
職務内容や配置変更のちがい
《正社員の場合》
Y社における職務内容や配置の変更範囲についてみると、正社員については配転が予定されていました。
《時給制契約社員の場合》
他方、時給制契約社員については、正社員のような人事異動はありませんでした。
仮に、郵便局を移る場合には、個別の同意に基づいて、従前の郵便局における労働契約を終了させたうえで、別の郵便局における労働契約を新たに締結することとなっていました。
契約期間のちがい
《正社員の場合》
正社員は、Y社と無期労働契約を締結していました。
《時給制契約社員の場合》
他方、時給制契約社員については、就業規則において、契約期間は6か月以内とされていました。
ただし、契約は更新できるものとされており、実際に、Xさんらの中には約10年の間、Y社に勤務していた人もいました。
| 正社員 | 時給制契約社員 | |
|---|---|---|
| 基本給 | 全国一律 | 地域別最低賃金の相当額に20円を加算した額を下限として、募集環境も考慮しつつ予算の範囲内で所属長が決定 |
| 寒冷地手当 | 勤務する地域の区分、世帯主か否か、扶養親族の有無によって金額が定められている | ×(不支給) |
| 人事異動 | ◯(配転が予定) | ×(人事異動なし) |
| 契約期間 | 無期 | 6か月以内・更新可能 |
訴えの提起
このような事情を背景に、Xさんらは、Y社が無期労働契約を締結している労働者に対しては寒冷地手当を支給する一方、有期労働契約を締結している時給制契約社員のXさんらに対しては寒冷地手当を支給しないことは、旧労働契約法20条に違反するものであると主張して、Y社に対して、損害賠償を求める訴えを提起しました。
何が問題になったか?
Xさんらが主張していたこと
Xさんらは、Y社が正社員には寒冷地手当を支給し、時給制契約社員には同手当を支給しないことが、旧労契法20条に違反すると主張していました。
旧労契法20条とは
旧労契約法第20条は、不合理な労働条件の禁止を定めたものです。
具体的には、同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止しています。
旧労働契約法20条
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
争われたこと
そこで、本件では、 “正社員に対しては寒冷地手当を支給し、時給制契約社員に対しては寒冷地手当を支給しないことが旧労契法20が禁止する不合理な労働条件の相違に当たるか否か?” が争いになりました。
裁判所の判断
裁判所は、正社員に寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいうことができず、旧労契法20条に違反するとは認められない、と判断しました。
判決のポイント
では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?
労働条件の相違が不合理か否かは賃金項目の趣旨が個別に考慮される
まず、裁判所は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の間に労働条件に相違がある場合、その相違が不合理であるか否かについては、両者の賃金の総額を比較することのみではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきである、という判断枠組みを示しています。
「労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者(以下「有期契約労働者」という。)と無期労働契約を締結している労働者(以下「無期契約労働者」という。)との労働条件に相違があり得ることを前提に、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情(以下「職務の内容等」という。)を考慮して、その相違が不合理と認められるものであってはならないとするものであり、職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解される。
そして、有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。(最高裁平成30年6月1日第二小法廷判決・民集72巻2号202頁参照)」
寒冷地手当の趣旨は継続的な勤務が見込まれる時給制契約社員にも妥当する
次に、裁判所は、寒冷地手当の主たる目的は、正社員の継続的な雇用を確保することにあると認められ、かかる趣旨に照らして考えると、時給制契約社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、寒冷地手当を支給することとする趣旨は基本的に妥当し、同手当を支給するとすることに合理的な理由があると言い得る、と判断しています。
「この点、Y社において正社員に対して支給されている寒冷地手当(…)の主たる目的は、正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、これらの一時的に増蒿する生活費を填補することを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと認められる。
上記目的に照らせば、寒冷地域において勤務する時給制契約社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、寒冷地手当を支給することとした趣旨は基本的に妥当するということができる。
そして、Y社における時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされており、Xさんらのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれていることからすると、正社員と同額を支給するかどうかはともかく、正社員と同様、時給制契約社員に対しても寒冷地手当を支給するとすることは合理的な理由があるといい得る。」
時給制契約社員は基本給の算定段階で生活費等を考慮した均衡が図られている
しかし、裁判所は、寒冷地手当には、正社員間の均衡を図り、これによって円滑な人事異動を実現する趣旨があるところ、他方で、時給制契約社員の場合には基本給の算定段階で生活費等を考慮した均衡がすでに図られている、と指摘しました。
「しかし、他方で、(…)正社員の基本給は、全国一律に定められていることから、寒冷地手当には、寒冷地域に勤務することにより冬期に発生する燃料費等の多額の出費を余儀なくされる正社員の生活費を填補することにより、それ以外の地域に勤務する正社員との均衡を図り、これにより円滑な人事異動を実現するという趣旨を含んでいることは否定できない。
これに対して、(…)時給制契約社員の基本給は、地域ごとの最低賃金に相当する額に20円を加えた額を下限額として決定されており、この地域別最低賃金額は、地域における労働者の生計費を考慮要素とし(最低賃金法9条2項)、具体的には、各都道府県の人事委員会が定める標準生計費等を考慮して定められ、その標準生計費を定める際には光熱費以外に灯油等への支出金額も検討材料とされている。したがって、具体的な金額は必ずしも明らかではないものの、寒冷地に勤務する時給制契約社員の基本給は、既に寒冷地であることに起因して増加する生計費が一定程度考慮されているといえる。
このように正社員と時給制契約社員との基本給は異なる体系となっている上、時給制契約社員の基本給は元々各地域の生計費の違いが考慮されており、寒冷地域に勤務することにより増蒿する生活費が全く考慮されていないものではない。」
寒冷地手当を支給するか否かはY社の経営判断に委ねられている
加えて、裁判所は、Y社の寒冷地手当が設けられた経緯等にも言及し、時給制契約社員に対して寒冷地手当を支給するか否か、その額をいくらにするか、はY社の経営判断に委ねられている、と判断しました。
「加えて、Y社における寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律200号)に由来するところ(…)、同法においても寒冷地手当の支給は、常時勤務に服する職員に限り支給するとされるにとどまり(同法1条)、時給制契約社員に対して寒冷地手当を支給する旨の規定はないことも考慮すると、前記認定事実の正社員と時給制契約社員との職務の内容及び職務の内容等の相違を踏まえ、時給制契約社員に対して寒冷地手当を支給するか否か、また、その額をいくらにするかという事項は、Y社の経営判断に委ねられているものといわざるを得ない。」
労働条件の相違は不合理ではない
以上の検討の結果、裁判所は、Y社において、正社員に寒冷地手当を支給するのに対し、Xさんのような時給制契約社員に寒冷地手当を支給しないという労働条件の相違が不合理とはいえない、と判断しています。
「そうすると、正社員に寒冷地手当を支給する一方で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件に相違があることは不合理であるとまではいうことができず、労働契約法20条に違反するとは認められない。」
労働条件に違いを設けるときは合理性の有無を慎重に検討しましょう
今回ご紹介した裁判例は、Y社が、正社員に対しては寒冷地手当を支給するのに対し、時給制契約社員に対しては寒冷地手当を支給しないという労働条件の相違が、旧労働契約法20条に違反する不合理なものであるか否か、が争われた事案でした。
裁判所は、従前の判例を参照し、「有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」との判断枠組みを示したうえで、Y社における寒冷地手当の趣旨や基本給の内容、同手当が設けられた経緯などを詳細に検討しています。
パートタイム・有期雇用労働法に注意
今回問題になった旧労働契約法20条は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)8条に引き継がれています。
(不合理な待遇の禁止)
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
同法を受けた同一労働同一賃金ガイドラインにおいて、「各種手当て」の支給の方法について次のとおり説明をしています。
役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければならない。
このガイドラインによれば、寒冷地に赴任する正社員にのみ支給する「寒冷地手当」も、同一の支給を行わなければならないと判断される可能性は大いにあると思われます。
本判決では、労働条件の相違が不合理なものとはいえないと判断されましたが、仮に不合理なものであると判断された場合には、当該労働条件は無効となるほか、会社が損害賠償義務を負うことになることにもなります。
手当の支給を検討する場合には、まず当該手当を導入する趣旨・目的を十分に検討したうえで、正社員に対してのみ当該手当を支給することが制度趣旨との関係で合理性を有するものといえるのか否かについても慎重に考慮しなければなりません。
弁護士にご相談ください
人手不足の中で、会社の魅力を高め、新卒採用に繋げようと、住宅手当や家賃手当、食事手当などの「手当」を新しい制度を導入する会社が増えています。
仮に、全社員に対して、同じように手当を支給するのであれば、特に大きな問題は生じません。他方で、一部の従業員に対しては支給し、他の従業員に対しては支給しないときや、支給額に差を設けるときなど、従業員間に差があるときは要注意です。
手当廃止の違法性が争われた事件、本件と同一争点で別の裁判所で審理された事件についての記事はこちらをご覧ください。
賃金体系や手当の支給についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)