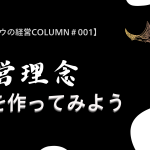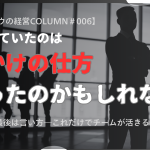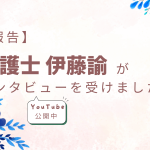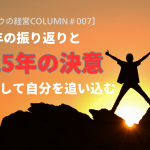商店街が抱える問題と企業経営の共通点
Recently updated on 2025-01-21

先日、私が所属する東京都中小企業診断士協会主催の講演会(新年会?)に出席してきました。
講師は、「ネイバーズグッド株式会社」社長の柴田様。同社はデザイン会社ですが、地域の商店街の振興やお祭りの運営サポートなど非常に面白い取り組みをされています。
聞いてみると、「商店街がかかえる問題」と「企業経営」の間には多くの共通点が見られるなぁと思いました。
特にノウハウや技術の属人化や、特定の意欲的な人物に負担が偏るという課題は、商店街や企業の規模を問わず共通して存在します。企業経営の視点からも、非常に多くの気づきを得ることができました。
今回、商店街の現状を通して、企業が直面しがちな課題と解決策について考察してみたいとおもいます。
直面する課題
商店街が抱える問題点のうち、企業経営にも共通する課題として共感したのは、次のような点です。
ノウハウや技術の属人化
商店街の現状
これまで永年続いてきたイベントは、地元商店街の方たちが試行錯誤を繰り返してきて工夫に工夫を重ねたものでした。前年の反省を活かし、新しい人を巻き込んでだんだんブラッシュアップしていくという進化を重ねて、よりよいものになっていくのが、よい循環でした。
ただ、コロナによって、イベントごとが中断すると、コロナ収束後も、高齢化した方たちの気力は残っていません。また、商店街のテナントがチェーン店ばかりになると、地元のイベントに参加してくれる人が少なくなります。こうしてそもそも新しい担い手が入ってこないということが続いてしまいます。
ノウハウは、イベントを支えてくれていた人たちの勘と経験のみにしか存在していません。長年のイベント運営や商業活動のノウハウが特定の人物や世代に依存しており、引き継ぎが十分に行われていない状況でした。特に、デジタル技術やSNS活用において新しい方法に適応できていないケースが見られます。
企業経営での類似点
会社の運営でも同様です。特定の社員に業務や知識が集中し、退職や異動によってその知識が失われてしまいます。特定の社員のみが築き上げたノウハウが属人化してしまうと、他の社員や将来の社員に引き継ぐことが難しいケースもあります。これは業務プロセスの透明性やドキュメント化の不足によるものです。
意欲的な人への負担の偏り
商店街の現状
そんな商店街に、意欲のある若い人が入ると、「若いからできるでしょ」と無邪気に結構重いタスクを振られることがあります。集計やって、SNS運用やって、動画つくって、など本来相当にコストを払わないとできないレベルのものを、それが得意な人に押しつけてしまう傾向があります。
そうした期待に応えていくと、イベント運営や企画に関して、熱意のある少数のメンバーに役割が集中し、その結果、過負荷となりやすい状況が生じています。この状態が持続すると、モチベーションの低下や離脱につながります。
企業経営での類似点
会社でも「できる人」や「やる気のある人」に業務が集中する現象がしばしば見られます。これにより、個人の負担が増え、燃え尽き症候群や離職のリスクが高まります。
対応策
さて、このような課題に対する、よく言われる対応策はおおむね次のような内容です。
属人化の解消
マニュアル化と共有化
商店街イベントの運営マニュアルやSNS活用のガイドラインを整備し、ノウハウを形式知として蓄積する。大規模イベントでは、各担当の役割分担を細かくマニュアル化することで、新規参加者でも容易に参加可能にする。
外部人材の巻き込み
若い世代や専門知識を持つ外部人材を招き入れ、持続可能な運営体制を構築する。
企業経営への応用
これらを企業経営に応用すると
- 業務フローの可視化とIT化(例:プロジェクト管理ツールの導入)により属人化を防ぎ、知識の共有化を進める。
- 社内教育やトレーニングプログラムを通じて、若手社員が新しい技術や知識を習得できる環境を整える。
といったところでしょうか。
負担の分散と対価の提供
役割分担の明確化
役割を細分化し、個々の参加者が負担を感じない範囲で関与できる仕組みを設計する。たとえば、ボランティア募集時には、「ゴミ拾いエリアの指定」「作業時間の明確化」などの具体的な指示を行う。
参加者への対価
無償ではなく、金銭的報酬やボランティア証明書の発行、交流の機会を提供することで、参加意欲を高める。
企業経営への応用
この点についての企業経営への応用としては、
- 各プロジェクトでの役割を明確にし、チーム全体で負担を分担する体制を作る。
- 特定の社員に過剰な負担がかからないよう、タスクを再配分し、必要に応じて外部リソースを活用する。
といったことが考えられます。
商店街と企業経営の未来に向けて
これらの課題というのは、規模の大小にかかわらず、少なからず存在するものです。なかなか表に出にくい不満というのは、経営者にとって予想できないタイミングで爆発することがあります。ガス漏れを普段のコミュニケーションによってタイムリーにキャッチして、適切にガスを抜いておかなければなりません。
本文中に述べた対策を取るに当たっても、経営者や役員が、メンバーそれぞれの納得感、公平感を調整しつつ、コミュニケーションを図って理解を得ていく必要がありますね。
自社? そうですね。私も足元からがんばります。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)