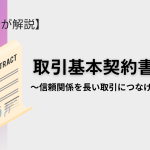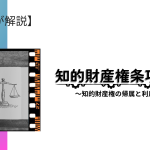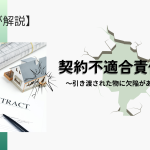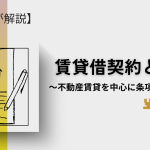ライセンス契約とは【条項例あり】【弁護士が解説】
他人から事務所や自動車など形のあるもの(有体物)を借りる契約は賃貸借契約です。ただ、他人の権利を借りる契約はなにも有体物に限りません。知的財産権などの無体物も借りることができるのです。このように、他人の知的財産権などの無体物としての権利を借りる契約を「ライセンス契約」といっています。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
ライセンス契約は、企業や個人が知的財産権を活用して収益を上げるために重要な手段です。本稿では、ライセンス契約の基本的な概念から、その種類や具体的な条項例、さらに実務上の注意点に至るまで、深掘りして解説します。
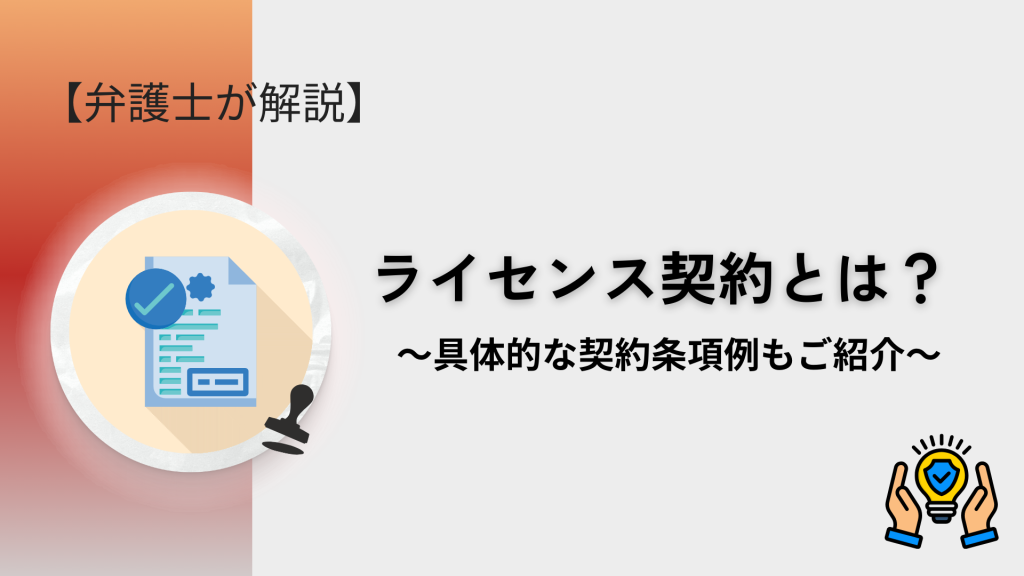
ライセンス契約とは?
ライセンス契約とは、知的財産権(特許権、著作権、商標権、ノウハウなど)を保有する権利者(ライセンサー)が、その使用を第三者(ライセンシー)に許諾する契約です。この契約により、ライセンシーはライセンサーが保有する知的財産を一定の条件下で利用できるようになります。
ライセンス契約は、権利の譲渡ではなく、使用を許可する契約である点が特徴です。そのため、知的財産権自体はライセンサーに残りつつ、ライセンシーがその権利を活用できるようになります。さらに、有体物を対象とする賃貸借契約と異なり、無体物である権利を対象とするライセンス契約は、同時に複数の人に「貸し出す」ことが可能になります。これにより、ライセンサーは自らの資産を最大限に活用し、ライセンシーは新たなビジネス機会を得ることができます。
ライセンス契約は、必ずしも「ライセンス契約」と明記していないことがあります。「著作権利用許諾契約書」、「商標権使用許諾契約書」などの名称であっても、第三者に権利の利用を許諾する契約ですので、実質はライセンス契約です。
他の契約形態との違い
ライセンス契約と混同されやすい契約形態には以下のようなものがあります。
販売契約
販売契約では、権利者が商品やサービスそのものを提供し、購入者はそれを完全に所有することになります。一方で、ライセンス契約では所有権は移転せず、使用許可のみが与えられます。
譲渡契約
譲渡契約では、知的財産権自体が完全に譲渡されるため、譲渡後の権利者は新しい権利者となります。これに対し、ライセンス契約では知的財産権は依然としてライセンサーに留まります。
フランチャイズ契約
フランチャイズ契約は、ブランド名や業務モデル全体の利用を許可する契約です。これに比べて、ライセンス契約は特定の知的財産の利用許諾に特化しています。
民法との関係
債権法改正時の議論において、ライセンス契約に賃貸借の規定を準用するということが検討されました。しかしながら、権利が複雑化した現代において、有体物を前提にした賃貸借の規定を準用するとなると、かえって法的安定性を欠くという意見が多く、結局、明文化は見送られ、当事者間の契約自由の原則に委ねるということになりました。
裏を返せば、契約当事者が、その具体的内容を契約書において詳細に規定する必要があるということになります。
ライセンス契約の種類
ライセンス契約にはさまざまな形態がありますが、代表的なものとして次のようなものを挙げることができます。
それぞれ、契約の内容に応じて、特許法、商標法、著作権法その他知的財産法による制約を受けることになります。
| 契約の種類 | 説明 | 代表的な業界・用途 |
|---|---|---|
| 特許ライセンス契約 | 発明の実施許諾 | 製造業、医薬品、機械工学 |
| 商標ライセンス契約 | ブランドやロゴの使用許諾 | フランチャイズ、アパレル、食品 |
| 著作物利用許諾契約 | 書籍、映像、音楽などの利用許諾 | 出版、映画、ゲーム |
| ソフトウェアライセンス契約 | ソフトウェアの使用許諾 | IT、SaaS、アプリ開発 |
契約条項ごとの実務ポイント
ライセンス契約において、特に重要な条項を解説します。以下、特許ライセンス契約を中心に必要に応じて他の契約についても見ていきます。
実施(使用)許諾条項
権利の特定
特許権の場合、基本的には特許番号と発明の名称を記載して特定します。他に、出願日、登録日、発明者などの情報が併記されることもあります。
商標権の場合、商標権の登録番号、商標の内容を記載して特定しますが、指定商品・指定役務の内容も明記しておいたほうが望ましいといえます。同一の商標であっても指定商品・指定役務が異なる商標として別に登録されていれば、別の商標権となります。
著作権の場合、特許権や商標権と異なり、何らの手続きを要しないで権利が発生する権利のため、権利の特定を工夫する必要があります。キャラクターや定義などで特定していく方法が一般的です。
許諾範囲の設定
本契約で権利の許諾する範囲を特定します。地域(日本国内か、特定地域に限るか)、期間(通常は、本契約の有効期間)など、制限がある場合はここで特定します。
ライセンス(実施権・使用権)の種類
特許権の実施権の種類には、専用実施権(特許法77条)と通常実施権(特許法78条)、通常実施権の中でも独占的通常実施権、非独占的通常実施権があります。通常実施権は対象となる特許、発明を独占的・排他的に実施する権利ですが、設定するためには登録が必要で、あまり使用されていません。
そこで、一般的に行われているのが、当事者間で特許権者がその実施権者以外の者に重ねて実施許諾を行わない合意をする「独占的通常実施権」の設定です。独占的通常実施権でない通常実施権は「非独占的通常実施権」と呼ばれています。「独占的」である旨を表示しなければ非独占的と解釈されますが、実務上、あえて「非独占的」と明記することが一般的です。
商標の場合、専用使用権(商標法30条)、通常使用権(商標法31条)に分類され、特許権の場合の考え方とほぼ共通です。
著作権の場合、著作権法63条1項で「著作者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる」とさだめ、法律上、専用許諾権のような独占的な形態の利用許諾を認めていません。したがって、ライセンシーに独占的ライセンスを付与する場合、独占的通常実施権と同時にライセンシー以外のものに対して利用を許諾しない旨の特約を定めることになります。
条項例
(特許権)実施許諾
1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、以下のとおり、本件特許に基づいて製造された製品(以下「本件製品」という。)を製造販売する通常実施権を許諾する。なお、本件契約における許諾期間中はライセンサーも本件特許を実施できないことを確認する。
(1) 本件特許
登録番号:第●●●●●●号(出願公開日:●年●月●日)
発明の対象:「●●●●」
(2) 実施内容:●●の製造、販売その他の処分
(3) 許諾期間
●年●月●日から●年●月●日まで
(4) 許諾地域
日本国内(ただし●●地域を除く。)
2. ライセンシーは、本件特許を第三者に再実施許諾することができる。
(商標権)使用許諾
ライセンサーは、ライセンシーに対し、以下のとおり、許諾地域内において、本商標を付した本製品を製造及び販売する非独占的な通常使用権を許諾する。
(1) 本商標
商標登録番号:第●●●●●号
定商品又は指定役務:●●●●
定登録日:●年●月●日
(2) 本製品
●●
(3) 許諾地域
日本国内(ただし●●地域を除く。)
(著作権)利用許諾
ライセンサーは、ライセンシーに対し、以下の各号のとおり、許諾地域内において、本件著作物を複製その他の方法により利用して本件製品を製造及び販売する非独占的な利用権を許諾する。
(1) 本件著作物
題号
種類(イラスト、漫画、映像、文章、音楽等)
著作者の名前
著作権者の名前
第一発行年月日
(2) 本件製品
●●
(3) 許諾地域
日本国内(ただし●●地域を除く)
ロイヤルティ(対価)の設定
ロイヤルティ(実施料、使用料、ライセンス料等実施許諾の対価)について、様々な方法が考えられますが、代表的なもののは概ね次のとおりです。
ランニング・ロイヤルティ(出来高払実施料)
売上や利益等の金額に、一定のパーセンテージをかけた金額をロイヤルティとして規定する方式(定率方式)です。製造や販売を行った製品1個あたりのロイヤルティの金額を支払う方式(定量方式)も存在します。
ランニング・ロイヤルティの場合、売上規模に応じた合理的なロイヤルティを設定できるというメリットがあります。ただ、ロイヤルティ算定方法については、お互い疑義のないよう明確に定めておく必要があります。
ランニング・ロイヤルティの場合、ライセンシーが製造や販売を行わなかった場合にライセンス料が発生しないことになり、特に独占的通常実施権を設定したライセンス契約において、ライセンサーの不利になってしまいます。そこで、ミニマム・ロイヤルティ(売上が生じていない場合でも一定額の支払義務を課すこと)と併用することが考えられます。
イニシャル・ペイメント
最初に一定額を支払う方式です。ランニング・ロイヤルティとの併用により、ある程度の開発費用等の回収を図ることができます。
ランプサム・ペイメント(一括払い実施料)
ライセンス契約を締結した時点で一定の金額をまとめて払い、その後の追加の支払を行わない方式です。
ライセンサーとしては、開発費用等を確実に回収できることになる反面、ライセンシーが予想以上の利益をあげたとしてもその恩恵にあずかれなくなります。
他方、ライセンシーとしては、利益をあげた場合それがそのまま自己の利益につながる反面、利益が思ったように伸びなかった場合、ロイヤルティの回収すらできなくなる危険があります。
注意点
技術の利用と無関係なライセンス料の設定
ライセンス技術とは無関係なライセンス料を設定することは不公正な取引にあたる可能性があります。
第4、5(2)
ライセンサーがライセンス技術の利用と関係ない基準に基づいてライセンス料を設定する行為、例えば、ライセンス技術を用いない製品の製造数量又は販売数量に応じてライセンス料の支払義務を課すことは、ライセンシーが競争品又は競争技術を利用することを妨げる効果を有することがある。したがって、このような行為は、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第11項、第12項)。
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
権利消滅後の制限
権利消滅後も利用を制限したり、ライセンス料の支払い義務を課すことは原則として不公正な取引にあたります。
第4、5(3)
ライセンサーがライセンシーに対して、技術に係る権利が消滅した後においても、当該技術を利用することを制限する行為、又はライセンス料の支払義務を課す行為は、一般に技術の自由な利用を阻害するものであり、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。 ただし、ライセンス料の支払義務については、ライセンス料の分割払い又は延べ払いと認められる範囲内であれば、ライセンシーの事業活動を不当に拘束するものではないと考えられる。
知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針
不返還条項
特許については、無効にすべき審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます(特許法125条)。そのような場合であっても既に支払ったライセンス料について返還しない旨の合意を定めておくことがあります。東京地裁昭和57年11月29日判決では、実用新案権が無効とされても不返還条項を有効と判断しています。
条項例
1. ライセンシーは、本件契約に基づく実施許諾の対価として、以下のとおりライセンサーに支払う。
(1) イニシャルロイヤルティ
金額:金●円(消費税別)
支払時期・方法:本件契約締結時に一括で支払う。
(2) ランニングロイヤルティ
金額:ライセンシーが販売した本件製品の販売価格●%(消費税別)
支払時期・方法:ライセンシーは、毎月末日時点において集計された当月分の本件製品の販売価格に基づき算出したロイヤルティに消費税・地方消費税を加算した金額を、翌月末日限り、ライセンサーの指定する銀行口座に振り込み支払う。振込手数料はライセンシーの負担とする。
2. 本件特許の無効審決が確定した場合、ライセンサーは前項に基づき支払われた対価のうち、イニシャルロイヤルティ全額及びランニングロイヤルティの50%を、確定日の翌月末日までにライセンシーが指定する方法で返還しなければならない。
実施報告・使用報告
ライセンサーがライセンシーの当該特許等の実施・使用状況を把握するための規定です。特に、ランニング・ロイヤルティによる対価設定をしている場合は重要で、ロイヤルティ算定の基礎となります。
また、商標ライセンス契約において、ライセンサーが自ら当該商標を使用しておらず、ライセンシーのみが使用している場合、不使用取消審判を避けるため、使用状況を把握しておく必要もあります。
条項例
ライセンシーは、ライセンサーに対し、毎月●日限り、本件製品における前月分の生産量、支払額及び販売量について書面で報告する。
表示義務・製造者表示義務
ライセンシーが本件商標を使用する際に,本件商標がライセンサーの登録商標であり、ライセンシーがライセンサーから使用許諾を得ている旨を表示する義務を定める規定です。
商標ライセンス契約においては、ライセンシーに登録商標の表示義務を課すことが一般的です。具体的な表示方法としては、例えば、商標の横に登録商標であることを示すⓇのマークを付したり、「○○[商標名]は○○[商標権者名]の登録商標です。」と記載したりすることが考えられます。契約締結時点で具体的な表示方法が既に決まっている場合は、本条において具体的な表示方法を特定して定めておくことも考えられます。
著作権ライセンス契約においても、著作権表示をすることにより著作権の所在を第三者に明らかにすることを求めることができます。
また、商標を表示する際、製造者の表示をしておかないとライセンサーが製造物責任を負う危険がありますので、製造者を明示する義務も規定することが望ましいと言えます。
条項例
1. ライセンシーは,本商標の使用に関し,本商品及びその広告宣伝物等において,本商標が登録商標であり,ライセンサーから使用許諾を得ている旨を表示するものとする。表示の方法については、別途ライセンサーが指定する。
2. ライセンシーは,本商標の使用に関し,本商品において,製造業者名を明記しなければならない。
ライセンシーは、本件製品を製造するにあたり、ライセンサーが指定する著作権表示をしなければならない。表示の方法については、ライセンサーが別途指定する位置に次の表示をする。
©(2025)○○
競業の禁止
独占的専用実施権・独占的専用使用権を目的とする契約の場合、ライセンサーがライセンシーとその商標に関して競業する事業を行うと、ライセンス契約の目的を損なう可能性があります。そこで、一定の範囲で競業の禁止を定める場合があります。
条項例
ライセンサーは、本契約期間中、ライセンシーとの事前の協議を行うことなく、許諾地域内でライセンサー自ら又は第三者を通じて本商標を使用したブランドライセンスビジネスを行わない。
表明保証
ライセンシーが、ライセンサーに対し特許権の有効性や発明の技術化的効果、第三者の権利の非侵害などについて保証を求める場合があり、その保証に反した場合契約の解除やライセンス料の返還などのペナルティーを負うことを定めることがあります。
もっとも、特許権については、事前に完全な調査を行うことはこんなんで、第三者の権利を侵害していないことを保証することが困難であるという事情もあります。そのため権利侵害を保証しないというケースもあり得ます。また、「(ライセンサーが)知る限り」と留保を付けて保証する場合もあります。
条項例
表明保証をする場合
ライセンサーは、ライセンシーに対し、以下の事項を表明し、保証する。
(1) 本契約締結時点において、本商標が有効に登録されており、当該登録が無効である旨の審決又は判決が存在していないこと
(2) 本契約締結時点において、本商標にかかる登録が無効である旨を指摘又は示唆する第三者からの通知を受領していないこと
(3) 本契約締結時点において、本商標に関して、いかなる訴訟、審判、仲裁、調停そのほかの手続も開始されていないこと
(4) 本契約に基づき本商標に関する通常使用権をライセンシーに許諾することについて、それと抵触する内容の第三者との契約が存在していないこと
表明保証をしない(非保証)場合
ライセンサーは、本特許権に係る無効理由の有無、本発明の実施に関する技術上、経済上、その他一切の事項、及び本実施品が第三者の保有する権利を侵害するか否かについて何らの責任も負わない。
不争義務
不争義務とは、ライセンシーが対象特許等の有効性を争った場合にライセンサーが契約を解除することができることを定める規定です。ライセンサーとしてはライセンシーとの間で対象となる特許等の有効性について争いになることを避ける目的で設定します。
また、第三者から特許無効の主張がなされた場合、特許権者は、特許発明について訂正審判(特許法126条)や無効審判の係属中に訂正請求(特許法134条の2)を行うことにより、それに対する対抗をすることが考えられますが、専用実施権者等の承諾を得た場合でないとこれらの訂正審判、訂正請求をすることができません(特許法127条、134条の2第9項)。したがって、ライセンサーが訂正審判や訂正請求をしたいときにライセンシーがその承諾を拒絶した場合も、契約を解除することで、ライセンシーとの紛争を回避する必要が生じます。
条項例
1. ライセンシーが、直接又は間接を問わず、本特許権の有効性を争った場合又はライセンサーが希望する訂正審判若しくは訂正請求の承諾を拒否した場合、ライセンサーは何らの催告も要せず直ちに本契約を解除することができる。
2. ライセンシーは、ライセンサーが本発明について訂正審判又は訂正請求をすることについて、異議なく承諾するものとする。
侵害の処置及び排除
ライセンシーは直接ライセンスの対象となる特許発明等を使用する立場であるため、競合企業等第三者が当該特許を侵害する事実を認識する可能性があります。そのため、ライセンサーとしては、ライセンシーがそのような事実を認識した場合は、速やかにその事実を知らせてもらう必要があります。
また、ライセンサーは、ライセンシーに対して、第三者の権利侵害の排除に関して、調査や確認等の協力義務を定めることで、特許権の維持を図る必要があります。
条項例
1.ライセンシーは、第三者による本特許権の侵害の事実を知ったときは、直ちにライセンサーに通知する。
2.ライセンシーは、ライセンサーが第三者による本特許権の侵害を排除しようとする場合には、甲に協力するものとする。
在庫品の取扱い
ライセンス契約が終了した後、本来であれば、ライセンシーは直ちに実施品の製造や販売を中止しなければならないことになります。また、仕掛品などがあった場合、廃棄する必要があります。
このような原則形態をそのまま採用することもできますが、他方で、ライセンシー側に在庫が残っている場合、不良在庫を抱えることになり、その負担が大きくなってしまいます。
そこで、契約終了後も一定の期間、在庫品の販売を認めたり、ライセンサーが買い取ったりすることが考えられます。
条項例
全量廃棄する例
本契約がその事由のいかんを問わず終了した場合、ライセンシーは、直ちに本実施品の製造を中止し、本契約終了時点で乙が有する本実施品及びその仕掛品を、ライセンシーの費用で廃棄しなければならない。
在庫の販売を認める例
本契約がその事由のいかんを問わず終了した場合、ライセンシーは、直ちに本実施品の製造を中止し、本契約終了時点で乙が有する本実施品及びその仕掛品を、ライセンシーの費用で廃棄しなければならない。ただし、ライセンシーは、本契約終了時点でライセンシーが有する本実施品の在庫に限り、本契約終了の日から●か月間、販売することができる。
弁護士に相談しましょう
ライセンス契約は知的財産の適切な活用に不可欠な契約ですが、契約内容次第で大きなリスクを伴います。また、個別性が極めて大きく、いわゆる「ひな形」が使いにくい類型の契約になります。特に、中小企業が契約を結ぶ際は、自社にとって不利な条件にならないよう慎重な交渉が求められます。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで
ライセンス契約の内容に不安がある場合や、自社に最適な契約条件を検討したい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

.png)