労働者とは【新時代の「労働者性」の見直し】

「労働者」とは誰か──フリーランス時代に再考する境界線
近年、フリーランスや副業といった多様な働き方が広がるなかで、「この人は労働者といえるのか?」という判断が、企業・行政・裁判所の現場でますます重要なテーマになっています。2023年に成立したフリーランス保護法(特定受託事業者法)も、まさにこうした曖昧な境界を背景に生まれた法律です。
本稿では、経営実務にも直結する形で「労働者とは誰か」を考えます。
なぜ「労働者とは誰か」が問われているのか
従来、日本の労働法は「雇用契約に基づいて働く者」を当然に保護の対象と想定してきました。しかし近年、請負契約・業務委託契約・個人事業主という形式で働く人々が増加し、名目上は自営業者でも実態は従業員同様に従属しているケースが少なくありません。
こうした人々を完全に「自己責任」として扱うのは実態に合わず、一方で一律に労働法を適用するのも現実的ではない――この間で法政策と裁判例の微妙な調整が続いています。
法律によって異なる「労働者」の定義
「労働者」という語は労働法体系の中心概念ですが、どの法律で使われるかによって意味が異なります。それぞれの目的に応じて保護範囲が広くも狭くもなっているのです。
| 法律 | 条文・リンク | 定義・特徴 |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 第9条 | 「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」。 使用従属性・賃金労働性を重視。最も基本的な定義。 |
| 労働契約法 | 第2条 | 「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」。 労基法と同趣旨。契約関係の明確化が目的。 |
| 労働組合法 | 第3条 | 「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入で労働する者」。 広い意味での経済的従属性を基準に、使用従属性を求める労基法より広い範囲を保護。 |
| 健康保険法 | 第3条 | 「使用される者」。雇用契約でなくとも事実上の使用関係があれば被保険者となりうる。 |
| 厚生年金保険法 | 第9条 | 代表取締役も被保険者となる場合があるなど、社会保険特有の広い概念を採用。 |
このように、労働基準法が「最低基準の適用範囲」を定める基礎であるのに対し、労組法は「団結の自由」を保障するためにより広く、社会保険法は「生活保障」を目的として事実上の使用関係を重視するなど、それぞれの立法目的に即した差異があります。
労働基準法上の労働者性──「使用」と「賃金」の実質
労働基準法における「労働者」判断の核心は、形式ではなく実態にあります。契約書上は「業務委託」「請負」と記載されていても、現実に会社の指揮命令下で働き、報酬が労務の対価として支払われていれば、労基法上の労働者と認定される可能性があります。
- 使用従属性:仕事の諾否の自由がない、勤務時間・場所・業務内容が使用者の指揮命令によって決まるか。
- 報酬の労務対償性:成果ではなく、労務提供そのものに対して定期的な賃金が支払われているか。
- 代替性の有無:他人に代替させる自由がなく、本人が直接従事しているか。
-
事業者性の欠如:設備や経費を自ら負担せず、会社側の資源を用いて働いているか。
判例法理でも、「労務提供の実態に照らし、経済的・組織的に使用者に従属しているか」が中核的判断基準とされています。とくに、外形的な雇用形態よりも、実質的に企業の経営組織に組み込まれているかが重要です。
ボランティア・家族従事者・外国人技能実習生などの周辺領域
労働者性が問題となる典型的な「グレーゾーン」として、以下のような類型が挙げられます。
- 無償ボランティア:報酬がないため労基法上の労働者には該当しない。ただし、実態が賃金労働に近ければ別。
- 家族従事者:同居の親族以外の従業員がいる場合、家族従事者であっても労働者性を肯定しうる(労基法116条2項の反対解釈)。
- 外国人技能実習生:従来「研修生」とされたが、実地作業の実態に照らして労働者性を認めた裁判例が多数。法改正により今後は「育成就労制度」に。
これらの裁判例は、形式的な契約区分ではなく、「賃金」「指揮命令」「従属性」の実態を重視している点で一貫しています。国籍や呼称を問わず、実際に働いて報酬を得ている者は、保護の枠組みから除外されないというのが近時の傾向です。
労働契約法・労働組合法上の労働者
労働契約法上の労働者
労働契約法は、労働者と使用者の契約関係を明文化した法律です。その第2条第1項は、労基法とほぼ同一の定義を採用しています。したがって、「労働契約上の労働者」と「労基法上の労働者」は原則として一致します。もっとも、裁判実務では、労働契約法の趣旨(契約関係の公正な形成・維持)に照らし、形式的な雇用関係にない者にも法理の類推適用を認めることがあります。たとえば、元請企業に下請企業従業員に対する「安全配慮義務」を認めたり(大石塗装・鹿島建設事件)、大相撲の力士と日本相撲協会の間に民法上の雇用関係があると認めることはできないとしつつ解雇処分を無効としたもの(日本相撲協会事件)があります。
労働組合法上の労働者
他方、労働組合法における「労働者」は、広い意味での経済的従属性があれば足り、使用従属性を求める労基法上の労働者より広い概念です。使用者と形式的な契約関係になくても、経済的に依存し、団体交渉を必要とする立場にある者は「労組法上の労働者」として認められます。
この点で、放送作家や専属ライター、タレント契約者、プロ野球選手などが「労組法上の労働者」とされた裁判例もあり、労働組合が交渉する相手方の範囲は広がりつつあります。
社会保険法上の「被保険者」との関係
健康保険法や厚生年金保険法における「被保険者」は、労基法上の労働者とはやや異なる独自概念です。特に、雇用契約関係の有無ではなく、事実上の使用関係が問われます。そのため、代表取締役でも実質的に会社に使用されている場合は被保険者資格が認められる一方、学生や短期労働者などは除外されるなど、社会保険制度上の特別な考慮が存在します。
このように、各法で「労働者」や「使用される者」の範囲を異ならせているのは、目的の違い(労働条件保護・団結権保障・社会保障給付など)に応じて柔軟に設計されているためです。
フリーランス保護法の登場──「労働者ではない人」への保護
2023年制定のフリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、従来の労働者概念の外にいた個人請負人にも一定の法的保護を与えるものです。対象は、他人を雇用せずに自ら業務を行う個人(特定受託事業者)で、企業から業務委託を受ける立場にある人です。保護の内容は以下のとおりです。
- 契約内容の明示義務(契約書面または電磁的記録による)
- 発注者による一方的な変更・解除の禁止
- 報酬支払の60日以内義務
- ハラスメント防止措置義務
この法律は、労基法的な「使用従属性」までは認められないものの、経済的依存関係に着目して保護を拡張したものであり、「労働者」と「自営業者」の間に新たな中間層を位置づけたと言えます。
経営者が注意すべきポイント
- 「業務委託契約」でも、実態が指揮命令下であれば労基法の適用対象となる。
- 形式的な成果報酬契約でも、実質的に時間給と同様なら残業代請求のリスク。
- フリーランス保護法による契約明示・支払期限義務を怠れば行政指導の対象となる。
- 雇用保険や労災保険の適用誤りは、遡及して保険料徴収・罰則の可能性も。
特に中小企業では、外注化・業務委託化の流れの中で「実は社員同様の扱いになっている」ケースが見られます。リスクを防ぐには、契約書作成時に実態を丁寧に分析し、必要に応じて雇用契約に切り替える判断が求められます。
まとめ──「契約書より実態」を見据えたリスクマネジメント
裁判所が一貫して重視するのは、契約書上の名称ではなく、実際の働き方の実態です。請負・業務委託・フリーランスという形式に安易に頼るのではなく、指揮命令関係・報酬形態・従属性などの観点から、客観的に「使用」関係が成立していないかを確認することが不可欠です。
働き方が多様化するほど、企業と個人の法的関係は複雑化します。適切な契約形態の選択と、労務リスクを踏まえた設計こそが、今後の経営における「見えないリスク」への最良の予防策です。
弁護士法人ASKでは、業務委託・雇用・フリーランス契約の区分整理、リスク診断、トラブル予防設計に関するご相談を承っています。
弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)
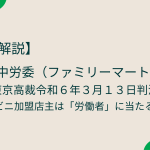

事件アイキャッチ-150x150.png)
事件アイキャッチ-150x150.png)