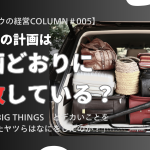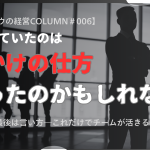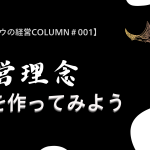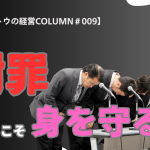企業変革のジレンマと構造的無能化:経営者が視点を変えるために
- イトウの経営Column
- tags: 企業変革のジレンマ 書評
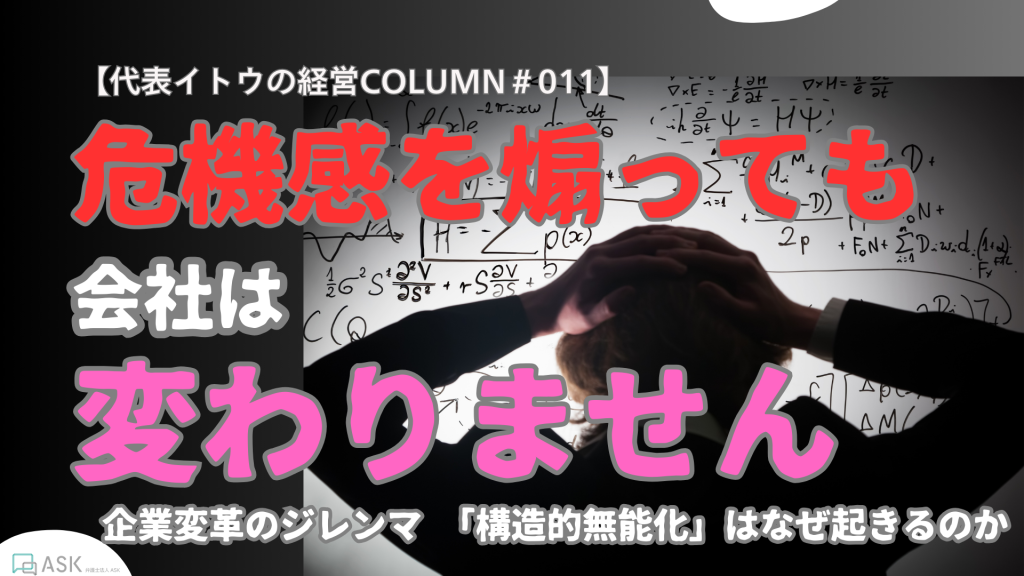
「企業を変革していかないといけないのに、みんなが全然ついてきてくれない」
変革の必要性を感じながらも、企業がなかなか動き出せない現象は、多くの経営者にとって共通の課題です。本書『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』では、この問題を深く掘り下げ、変革が停滞する理由とその克服方法について考察しています。
経営者なら誰もが共感できる(グサグサ刺さる)良書です。覚悟してお読みください。
変革の障壁は「危機感不足」ではない
経営者は「変わらなきゃいけない」と常に思っています。危機感があるから。 で、変わらない人を見ると「危機感が足りないんじゃないか」という評価になりがちです。
「変わらなければならないという危機感が足りないのではないか」 この言葉には、実は様々な意味が込められている。 皆がこの状況をわかっていないのではないか、という焦り。状況をわかっていないから変わらないのだ、という苛立ち。
危機感を煽ることが変革の第一歩とされることが多いですが、それが必ずしも有効でないことを指摘しています。むしろ、危機感の醸成だけでは問題の本質を見誤る可能性があります。
危機感があれば会社が変わるわけではない。
多くの企業が直面しているのは、「どうすればよくなるのか、どこから手をつければいいのかがわからない」という状態です。
このような状況では、単に危機感を高めるのではなく、変革に向けた具体的なアクションを示し、それを企業全体で共有することが求められます。
「わかる」とは、「わからないことがわからない」ということでもある。なぜなら、何かがわかるということは、別の解釈の可能性を考えないことによって成り立っているからだ。
「わかった」といっている人の方が危険かも知れません。
なぜ新規事業は失敗するのか
多くの企業で新規事業が定着しない理由の一つは、過去の失敗がトラウマとなり、社内で挑戦する風土が生まれにくいことです。
事業部門から「こんな事業をやりたい」と手を挙げる人があまり出てこない。その背景には、過去に本社の呼びかけで新規事業開発に挑戦したにもかかわらず、成果が芳しくなかったため、その取り組みが雲散霧消してしまったことも影響していた。
この状況を打開するためには、新規事業開発の取り組みを単発で終わらせず、組織として持続可能なプロセスにする必要があります。企業が失敗を恐れずに挑戦できる環境を整え、試行錯誤が許される文化を醸成することが重要です。
「風土の問題」に逃げない
新規事業がうまくいかないと、「社内風土が悪い」「社員の意識が低い」といった説明がされがちです。しかし、本書ではこのような考え方に警鐘を鳴らしています。
今までは、正体がわからないものを勝手に「風土の問題」「意識の問題」だと思い込んでいた。だが、そもそも風土も意識も、捉えどころのない何ものかに名前をつけて、問題の複雑さを見ないようにしていただけではなかったか。
問題を単純化せず、構造的な要因を探る視点が重要です。なぜ組織が動かないのか、どのような力学が働いているのかを深く掘り下げることが求められます。これには、データを基にした客観的な分析や、組織の各層での対話が必要です。
企業変革とは試行錯誤のプロセスである
本書は、変革は明確な成功ルートがあるものではなく、「成果につながるかどうかもわからない試行錯誤の過程こそが企業変革である」と強調します。
また、コッターの「企業変革の8段階」理論に触れながら、変革の前提条件として「組織の問題を個人の意識の問題として矮小化しない」ことが重要であると指摘しています。
変革のための試行錯誤を許容し、それを継続できる仕組みを整えることが、企業に求められる姿勢です。
変革を進めるための具体的アプローチ
では、変革を成功させるために経営者は何をすべきなのでしょうか。
1. 戦略の明確化
- 変革が進まない理由の一つは、「戦略が明確になっていない」ことにあります。
- 戦略とは、単なる目標の提示ではなく、「困難な課題を解決するために設計された方針や行動の組み合わせ」であるべきです。
2. 部門横断的な対話の促進
- 「変革を進めるには、部門・部署の違いを超えて一緒に考えることが重要」
- 「自社の事業の顧客にとっての価値は何か」「新規事業の顧客は誰か」といった基本的な問いを考え直すことが求められます。
- 組織内での壁を取り払い、柔軟なコミュニケーションを促進するための仕組み作りも欠かせません。
3. 組織内のナラティヴ(物語)の共有
- 組織のメンバーが変革の意味を理解し、共感するためには、「ナラティヴを共有する」ことが鍵となります。
- これは単なるビジョンの提示ではなく、「なぜこの変革が必要なのか」を経営陣自身の言葉で伝えることが求められます。
変革の主体者としての視点の転換
企業変革を成功させるためには、「変わらないことへの苛立ち」ではなく、「変革を生み出すための環境づくり」に経営者が目を向けることが不可欠です。
本書の示唆する通り、単に危機感を煽るのではなく、
- 問題の本質を捉え直し、
- 組織全体で対話を重ねながら、
- 戦略とナラティヴを共有する
このような取り組みが、企業の未来を形作る鍵となるのではないでしょうか。
「企業を変えていかないといけない」と漠然と思っているんだけど、なかなか形にならないとお悩みの経営者の方々。
まさに自分のことをいわれているかのように、グサグサと刺さりまくる一冊でした。